英語の勉強は,“I am a boy. This is a pen.”から始まりました。はるか昔の話です。若い英語の先生が,英語特有の巻き舌で教科書を読み,生徒がそれに合わせて音読したことを思い出します。それ以来英語と付き合ってきました。その道は平坦ではなく,高い山を頂上に向かって一歩ずつ登っていくようなものでした。それは今も続いています。英語の高みを目指すには登り続けるしかありません。強い意志をもって努力し続ければ,必ず目標が見えてきます。「継続は力なり」です。
このエッセイでは,私がこれまで英語をどのように学んできたか,どのようにして自分なりの勉強法を見つけてきたか,さらにそれが英語学習者にとって共通の学びの方法になり得ることをお話しします。題字に「理系研究者」をつけたのは,ちょっとしたきっかけで英語が好きになった筆者がこの職業につき,仕事に英語を生かしながら英語を学び続け,今に至っていることを知ってほしいとの思いからです。
このエッセイが皆さんにとって英語力向上への一助になることを願っています。
外国人との文通で英語が好きになったー英語文通の勧め(その1)
今はインターネットの時代である。オンライン上で瞬時にメッセージを交換できる。手紙を書くことなど遠い昔の話しになった感がある。とりわけ若者の間には手紙を書くという発想さえ存在しなくなりつつあるようだ。
かつては外国とのやりとりは航空便が主流だった。封書を送る国にもよるが,航空便が相手に届くまでは約1週間を要した。気の長い話である。
中学時代,外国のペンフレンドとの文通が流行していた。文通,ペンフレンドという言葉自体がもはや死語になりつつあるが,文通はペンフレンドと手紙をやりとりすることである。当時ペンフレンドの協会に入会すれば,日本人との文通を希望する外国人の名前と住所,短い紹介文が掲載された機関紙が送られてきた。その中から希望する相手を選び英語の手紙を送るのである。
私も数人に手紙を送った。始めは返事が来るが,しばらくするとほとんどの人とのやり取りは途絶えた。しかし唯一ドイツ人のローラという女の子との文通は続いた。遠い国からの手紙は,外国人に会ったことのない田舎の少年にとっては,外国への興味をかきたてるには十分だった。家族のこと,日常生活,学校での出来事などを書いて送った。ある時,彼女の中学校の英語の授業で,日本の友達からの手紙を皆に紹介したという手紙をもらった。少し得意な気持ちになった。高校生になったときベルリンの壁の絵葉書が届いた。東西に引き裂かれたドイツの人々の現実に思いをはせた。
今考えると手紙の英文はつたないものだっただろう。それでも学校で習った英語の知識を総動員して書いたことを思い出す。それが結果的には英語の成績の向上につながり,英語が好きになった。
最近,私の住む街の高校で,生徒たちが文通を通じてアメリカの高校生と交流しているという話を聞いた。彼らはこの活動は通じて英語を好きになり,それが英語をもっと勉強しようという動機につながっていると思う。
以前,元通訳者の鳥飼玖美子氏の講演を聞く機会があった。英語によるコミュニケーション上達法の1つとして,興味のある内容に特化した英語を自ら学習し,それを通じてコミュニケーションを向上させる方法の重要性を指摘された。英語で手紙を書くことは,そうしたコミュニケーションの1つと言える。
今の時代,手紙に代わりインターネット上のコミュニケーションが主流だ。日本人研究者が同じ分野の外国人研究者と英語のメールで情報を交換し,ビジネスマンが外国人と仕事上のメールのやり取りをするのは日常となっている。日常的に英文を書くことが英語の上達に大いに役立つ。
インターネットで調べてみると,オンラインで外国人と英語で手紙のやり取りができるペンパルアプリやウェブサイトがあった。現代版の文通である。これをうまく利用すれば,英語の作文力が向上し,英語を勉強しようという意欲が高まるだろう。
受験勉強は英語力向上に大いに役立つが,勉強には工夫が必要(その2)
高校に入ると英語の教科書の内容が急に難しくなったように感じた。知らない単語がどんどん出てくる。予習のために単語の意味を辞書で調べ,英文の意味を理解するのに相当の時間がかかった。当時使った英和辞書の単語には赤線が引かれ,表紙はボロボロになっていた。覚えた単語のページを破り,口に入れて飲み込むなどという嘘のような話も聞いた。それほど多くの生徒が必死に単語を暗記したということだろう。
今のように電子辞書はないので,単語だけ調べて授業に臨むとこともしばしばあった。英語以外の科目の予習復習もあるので,英語を味わうなどという余裕はなかった。試験前になると単語をひたすら覚え試験に備える。その繰り返しだった。今思えば,高校に入った時点で,英語も他の科目と同様大学入試に向けた体制に組み込まれていた。
授業では英文解釈が中心だった。先生が教科書の英文を読みながら和訳し解説する。生徒はひたすら大切なところをメモし,板書を写す作業をする。英語の参考書でもかなり高度な英文が出てきて,それを必死で解釈し問題に解答した。
当時の英語の授業は,英文和訳が中心であり,現在強調されているコミュニケーションのための英語という考え方はほとんどなかった。だからといって英文解釈中心の教育が英語のコミュニケーションに役立たないなどということはない。
ビジネスの世界では英語の文書を読み取り,正確なビジネスレターや文書を書かなければならない。稚拙な文章はビジネスの内容を疑われてしまう。研究の世界でも多くの文献を読んで理解し,読者を説得できる論文を書くことが求められる。また,英語の会話で政治,経済,社会,文化などを話題にするとき,日常会話に比べより多くの語彙,高度な英語の表現が必要である。高校で習う英語は,このような状況に対応できるレベルの内容をかなり含んでいる。高校英語をマスターすれば,英語を必要とする仕事のさまざまな場面で大いに役立つだろう。
ただ,高校の英語を勉強するとき工夫し,改善すべきことはある。私の高校時代,声を出して英語を読む,つまり音読することはほとんどなかった。ましてや英語のリスニングやスピーキングなど皆無だった。翻って現在の英語教育はどうか。英語によるコミュニケーションが重要視されるようになり,英語教育の内容は変わったと言われている。しかし,状況は本質的に50年前とあまり変わっていないのではないかと思ったことがある。
大学で科学英語という科目を受け持っていた。環境科学に関する教材の英文を学生に音読してもらった。意味はきちんと理解しているのに多くの学生がすらすらと音読できない。おそらく中学,高校では英語を音読することはほとんどなく,ひたすら黙読してきたと思われる。
音読といえば同時通訳者の草分けである國弘正雄氏の言葉を思い出す。氏は中学時代に教科書をお経のように音読し,それがプロとしての仕事に大きく役立ったと述べている。
英語を声を出して読む。これは英語学習の基本である。また,今の時代,単語の意味はスマホや電子辞書で調べられるし,ほとんどの教科書や参考書にはデジタル教材がついている。それらを活用して音読し,さらにリスニングを強化すれば,英語力はさらに高まる。
英文法をおろそかにしてはいけない(その3)
現在高校で英文法の授業が独立して行われているかどうか知らないが,私の時代には週に1時間英文法の授業があった。英文法が英語の読解には重要だとわかってはいたが授業は退屈だった。とはいっても試験に備えるためにはそれなりに勉強した。
わが国の英語教育はあまりに文法に重きを置きすぎている,もう少し実際の会話で使えるような教育をやるべきだという声を聞くことがある。英語を話す能力を向上させることは重要だ。だからといって文法をおろそかにしていいというわけではない。
私たちが日本語を話すとき意識していなくても日本語の文法に沿って話している。英語国民も同様だ。英語という言語は日本語以上に文法が厳密であり,それが話し言葉にも反映している。日本語に比べ文法的なあいまいさが少なく,それが話し言葉にも表れる。英語の文法を軽視すれば,ブロークンな話し方になってしまう。
英語を必要とする仕事に就いたとき積極的に英語を話すことは大切だが,できるだけ大人の話し方を心がけて欲しい。文法を無視した稚拙な話し方だといつまでたっても英語は上達しない。
ビジネスの書類,技術報告,学術論文などを書くときはなおさらだ。文法的に正しい,論理的な文章を書くことがますます重要になってくる。稚拙な文章は読む人をいらいらさせるし,そのような報告書や論文は正当な評価を得られない。
現役のとき学術雑誌に英語の論文を投稿する際には,文章は文法的に正しいか,論理的な構成になっているかを徹底的に検討し,何回も何回も書き直し,最後は英語ネイティブの専門家に見てもらった。このような体験を通じいかに文法が重要であるかを改めて認識した。
仲間と一緒に学べばやる気が出る(その4)
大学に入学しても英語の授業はリーディングが中心で,授業形態は高校時代とほとんど同じだった。ただ,1年生のとき実用英語のクラスが一つだけ開講されていた。人数制限のため受講希望者にはリスニング試験が課された。受験したが見事に落ちてしまった。
そこでアメリカ文化センター(現アメリカンセンター)で開講されている英会話クラスを受講することにした。クラス分けテストを受けた。これまで英語を聞き,話す練習など全くしたことがないので,初級クラスだった。それでも生まれて初めてアメリカ人の先生から習う英語である。興奮した。1年位続けると少しずつ話せるようになり上のクラスに上がった。しかし,英語が思うように口から出たこなかった。クラスには上手に話すクラスメイトがいて刺激になった。これは仲間と学ぶことの大きな利点だ。一人で勉強するとつい挫折しそうになるが,仲間がいるとがんばろうという気持ちになる。
やがて市内に英会話学校が出てきたので,アメリカ文化センターの英会話クラスは役目を終えた。私も市内の民間の英会話クラスに通い始めた。クラスには,中学校の英語の先生,旅行の添乗員,郵便局員,大学の先生,会社員など,さまざまな職業の人が在籍していた。その頃,私は仕事についていたが,クラスメイトとの交流は英語の学習と同じくらい楽しく,刺激になった。
仕事で英語の研究論文を書く必要性にせまられたので,英会話だけでなく英作文のクラスにも参加した。講師のサボタ先生が,アメリカの大学で使われる”The Writer’s Options-College Sentence Combining” という教科書を使って私たちを鍛えてくれた。添削は自分の英文の弱点を見直す上でとても役立った。やがてスクールの事情で英作文のクラスはなくなったので,クラスの有志でサボタ先生を雇って,公民館でレッスンを続けた。
今の時代,英語コーチング,自学用アプリ,オンライン英会話など,自分が若いころには考えられないような様々な英語学習の手段がある。これをうまく利用すれば英語力は確実に伸びると思う。私もこれらツールのいくつかを利用している。
ただ,対面の英会話クラスで勉強したり,英語が好きな仲間が集って互いに刺激を受けて英語力を伸ばす,という英語の勉強法は今でも色あせていない。私自身,NHKの実践ビジネス英語(2021年から現代ビジネス英語)を勉強する会に十数年前から参加している。最近,各自がテーマを持ち寄り,ネイティブを含めた参加者が英語で議論するグループにも参加している。
一度,英語の好きな仲間が集う場に参加してみませんか。きっと何かが得れれますよ。
英語ネイティブの友達をつくる(その5)
英語ネイティブの人と友達になって,英語力を伸ばそうと思った。市内に国際交流センターがあり,そこでは外国人にさまざなな情報が提供されていた。その一角に日本人や外国人がメッセージを掲示できるコーナーがあった。1980年代,インターネットはまだ普及していないアナログの時代である。「英語と日本語の交換パートナーを求む」というメッセージを具体的な内容とともに掲示した。
しばらくして1人のアメリカ人男性から連絡があった。彼は市役所で支援員をしていた。アメリカにある大手の航空機製造企業で働いた後,来日した。日本語があまり話せず,日常生活で寂しい思いをしていたようだった。アメリカでの仕事のこと,現在の職場のこと,家族のことなど様々な話題について話した。私の小さい息子を連れて一緒に海水浴に行ったこともあった。
あるとき個人的な悩みを相談された。日本人女性とつきあっているけど両親がいい顔をしないという。外国人とのカップルがまだ少ない時代,両親がそう思ったのも無理はない。私のアドバイスが役に立ったかどうかわかないが,その後両親の承諾を得て二人は結婚しアメリカに旅立った。その後日本への里帰りの折,子どもを連れて私の家を訪ねてくれた。うれしい気持ちでいっぱいだった。
手元に新聞記事がある。「1年間,市職員や中高校生に“本場の英語”を指導してきた米国カリフォルニア州の3人の青年が今月末でその任務を終え,帰国。市長から感謝状が贈られた」。彼もその一人だった。
今の時代,インターネット上で言語交換をするためのさまざまなサービスやアプリがある。外国人と瞬時につながり話ができる時代が来るなどとは当時想像もしなかかった。このような文明の利器を使わない手はない。デジタル機器をうまく活用することで英語力はおおいに伸びると思う。
興味のある分野の英語を読んで英語力を高める(その6)
私たちは日々日本語で本や雑誌,新聞,インターネットなどの記事を読んでいる。多くの場合,本や記事を読むのは,その内容に興味や関心があるからだ。英語を読むときも同じである。興味のない英語の本や記事を義務的に読んでも面白くないし,理解も深まらない。内容に興味があれば,少々わからない箇所があっても持てる知識を総動員して理解しようとする。それが満足感につながり英語力が高まる。
昔からアメリカのTIME誌を読めるようになりたいと思っていた。ある時奮起して読み始めたが長続きしなかった。なぜ挫折したのか。それは,記事の内容への興味の如何にかかわらず,英語の勉強のために義務的に読もうとしていたからだ。
その後TIME誌に再度挑戦した。コロナで外出が制限された時期である。早朝,静寂の中で雑誌のページをめくり,面白そうな記事を選んで読み始めた。アメリカでコロナが猛威を振るう中多くの人が家族の死に直面し,エッセンシャルワーカーが必死で任務に当たっている様子が臨場感をもって伝わってきた。まるでその現場にいるような錯覚に陥った。読むことは,筆者の思いを共有する行為であることを認識した。この醍醐味こそが英語力強化のカギとなる。
仕事で使う英語は,面白いというより必要性に迫られて読む場合がほとんどだろう。それでも内容が理解できれば仕事がスムーズに進むので,英語を読もうという意欲が高まるはずだ。
私にとって,英語で本や論文を読むことは研究者への第一歩だった。学部学生のころは自分の専門分野の英書はほとんど読んだことがなかった。大学院に入ってはじめて関連する英語の本や文献を読み始めた。一日に読むページ数を決めて土質力学の英書を読んだ。専門用語は初めはわからなくても,同じ用語が頻繁に出てくるので自然と覚えてしまった。自然科学の英文は論理的で,主観的な表現はほとんど使われていないで,土質力学の考え方をよく理解できた。この経験は英語の文献を読むのに大いに役立った。
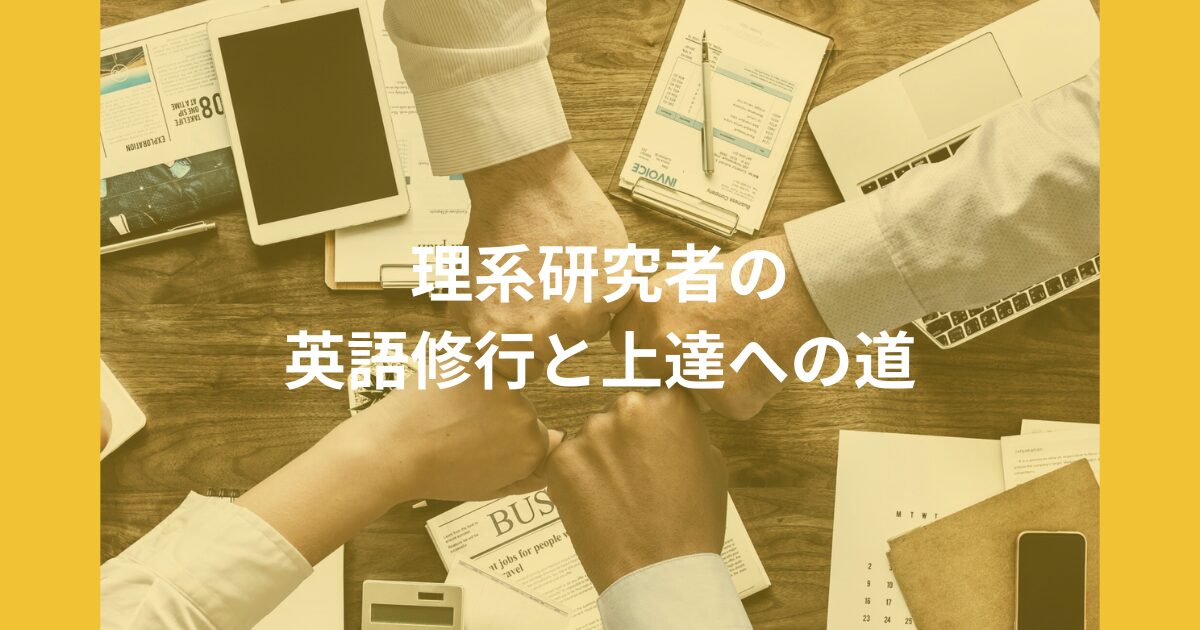
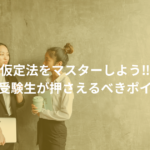

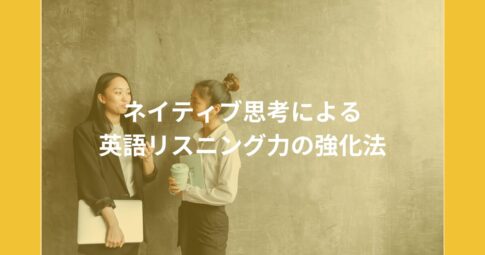
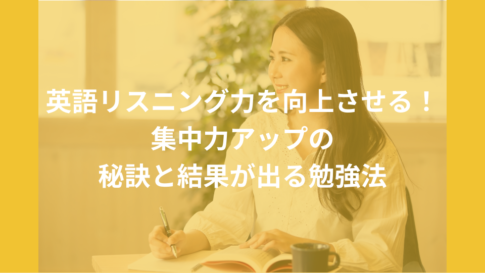
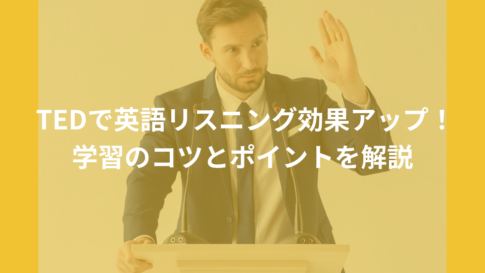
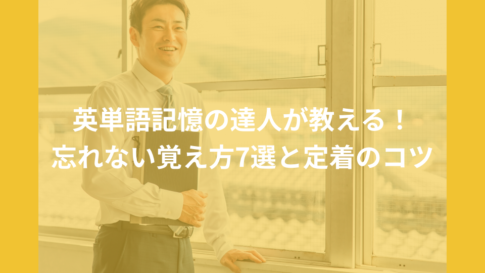
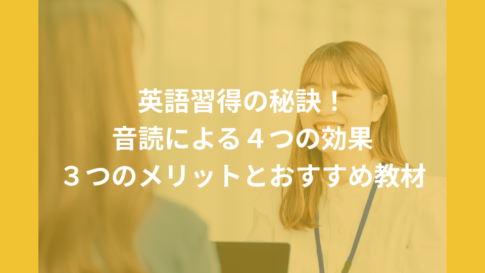

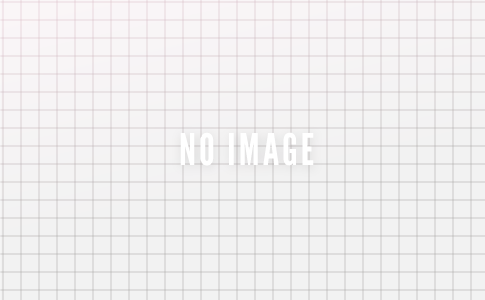
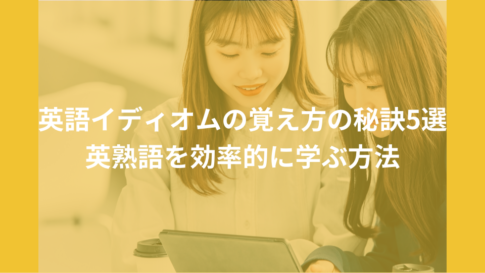
大学で35年間教育と研究に従事し、その間、英語による講義、留学生指導、英語論文の執筆、翻訳、国際交流など、英語に関係する業務に携わってきました。退職後、英語教授法のプログラム(カリフォルニア大学)と会議通訳者養成講座(全国学術会議通訳者連盟)を修了しました。そして社会人への資格試験(英検、TOIEC)の指導、中学生への英語指導を行ってきました。
九州大学農学部卒業
・同大学院修士課程修了
・農学博士
・35年間九州大学で教育研究に従事
・カナダマギル大学、イギリスウェルズ大学で研究に従事、ベトナム、インドネシアで
JICAプロジェクトに参加
・英検1級取得
現在 九州大学名誉教授